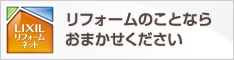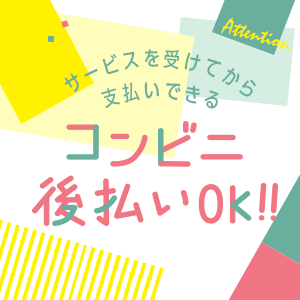水のコラム
止水栓から水漏れ!原因と対処法を愛知の水道職人が徹底解説

キッチンや洗面台の下から水が染み出している、トイレの床がいつも濡れている、そんな経験はありませんか?止水栓からの水漏れは発見が遅れがちですが、放置すると大きな被害につながるため、発見したら素早い対応が必要ですます。本記事では、止水栓の水漏れについて原因から対処法まで詳しく解説します。
目次
止水栓の水漏れを放置すると起こる深刻なトラブル
止水栓からの水漏れは目立ちにくいため、つい放置してしまいがちです。しかし、水道料金の増加や建物への被害、階下への漏水など、様々な問題を引き起こす可能性があります。早期発見・早期対処が被害を最小限に抑える鍵です。
シンク下や洗面台下など、普段目につきにくい場所での水漏れは、気づいたときには既に大きな被害になっていることも少なくありません。収納している物が水浸しになったり、床材が腐食したりする前に、早期発見・早期対処が重要です。
水漏れの量は少なくても、長期間続けば相当な水量になってしまいます。特に集合住宅にお住まいの方は、階下への漏水という最悪の事態も考えられます。
また、湿気によるカビの発生も深刻な問題です。カビは健康被害を引き起こすだけでなく、一度発生すると完全に除去することが困難なため迅速に対処しましょう。
止水栓の水漏れに気づいたら最初に確認すべきこと

止水栓からの水漏れを発見したら、まず冷静に状況を確認しましょう。慌てて誤った対処をすると、かえって被害を拡大させてしまうことがあります。
止水栓と元栓の違いを理解しよう
水道設備には「止水栓」と「元栓」という2種類の栓があり、それぞれ役割が異なります。
止水栓は、キッチンや洗面所、トイレなど、水を使用する各場所に設置されている小型の栓です。その場所の水だけを止められるため、修理やメンテナンスの際に便利です。
一方、元栓は建物全体への給水を管理する大元の栓で、水道メーターの近くに設置されています。元栓を閉めると、家中すべての水道が使えません。
止水栓の修理は水道修理業者が対応しますが、元栓(給水装置)に関する問題は、基本的に水道局が管理しています。この違いを理解しておくと、トラブル時の対応もスムーズです。
止水栓を活用すれば、例えばトイレの修理中でもキッチンでは水が使えるため、生活への影響を最小限に抑えられます。
水漏れしやすい止水栓の設置場所
止水栓は水回りの各所に設置されていますが、その場所は設備によって異なります。
キッチンでは、シンク下の収納スペース内に設置されているのが一般的です。扉を開けると、給水管と給湯管それぞれに止水栓が取り付けられています。ただし、古い住宅では点検口の奥に隠れていることも多いです。
トイレの止水栓は、タンクへの給水管の途中、壁や床付近に設置されています。タンクレストイレでは便器内部に収納されていることもあるため、取扱説明書で確認しましょう。
洗面台では、洗面ボウル下の収納内に設置されているケースがほとんどです。浴室の場合は、水栓本体に内蔵されているタイプや、点検口内に設置されているタイプがあります。
これらの場所は日常的に目にすることが少ないため、定期的な点検の折に位置を確認しておくよう心がけておくといざという時慌てません。特に水道トラブルが起こりやすい築年数の経った住宅では、止水栓周辺の確認を習慣づけるとよいでしょう。
止水栓から水が漏れる5つの原因

止水栓からの水漏れには、いくつかの典型的な原因があります。原因によって対処法も異なるため、まずは何が原因なのかを正しく把握することが重要です。
地震後に多いナットの緩み
地震があった際、止水栓と配管を接続している部分のナットが緩み、隙間から水が漏れ出すケースが多いです。
地震の揺れによって配管に力が加わり、接続部分のナットが緩んでしまうのです。震度3程度の地震でも、建物の構造や配管の状態によっては影響を受けることがあります。
ナットの緩みによる水漏れは、最初はポタポタと垂れる程度ですが、放置すると徐々に漏水量が増えていきます。手で触ってナットがグラグラと動くようであれば、緩みが原因の可能性が高いでしょう。
この場合の対処は比較的簡単で、適切な工具でナットを締め直すだけで解決することが多いです。ただし、締めすぎると配管を傷めてしまうため、適度な力加減が必要です。
地震の後は、目に見える被害がなくても、念のため水回りの点検を行うことをおすすめします。
築10年前後で起きやすいパッキンの劣化
止水栓内部には、水を止めるためのゴム製パッキン(三角パッキンやコマパッキンと呼ばれる部品)が使われています。
このパッキンは、新品の時は弾力性があり、しっかりと水を止める役割を果たします。しかし、10年前後経過すると、ゴムが徐々に硬化して弾力を失い、水を完全に止めることができなくなります。
パッキンの劣化による水漏れは、止水栓のハンドル付近からじわじわと水が染み出すのが特徴です。止水栓は蛇口と違って頻繁に開閉しないため、摩耗による劣化は少ないものの、経年劣化は避けられません。
実際、止水栓からの水漏れで最も多い原因がこのパッキンの劣化です。特に、長年一度も交換していない止水栓では、いつ水漏れが始まってもおかしくない状態と考えてよいでしょう。
パッキンは消耗品として、定期的な交換が推奨されています。10年を目安に交換し、水漏れトラブルを未然に防ぎましょう。
バルブ(開閉弁)の破損
止水栓の中核部分であるバルブ(開閉弁)が破損することで、水漏れが発生することがあります。
バルブは水の流れを制御する重要な部品で、開閉を繰り返すうちに摩耗したり、経年劣化によって亀裂が入ったりすることがあります。特に、長期間使用していなかった止水栓を急に操作すると、固着していた部分に無理な力がかかり、破損することも少なくありません。
バルブの破損による水漏れは、止水栓の開閉部周辺から水が少しずつ滲み出てくるのが特徴です。ハンドルを回しても水が完全に止まらない、または開閉が困難になっているという場合は、バルブの破損を疑ってください。
この場合、パッキン交換だけでは解決せず、バルブ部分の交換が必要です。交換作業には専門的な知識と技術が必要なため、無理をせず専門業者に依頼することをおすすめします。
バルブの破損を防ぐためにも、定期的に止水栓を開閉して、動作確認を行うことが大切です。
ニップル管の腐食による水漏れ
止水栓を壁や床に固定するために使用されるニップル管が腐食することで、水漏れが発生するケースも多いです。
ニップル管は金属製の短い配管で、止水栓と建物の配管をつなぐ役割を果たしています。築年数の古い建物では、ニップル管が腐食して穴が開いたり、ヒビが入ったりすることがあります。
腐食による水漏れは、止水栓の根元付近から水が染み出すのが特徴です。見ただけでは分かりにくいですが、触ると湿っていたり錆が浮いていたりすることで発見できます。
特に湿度の高い場所や、結露が発生しやすい環境では、腐食が進行しやすいです。また、水質によっても腐食の進行速度は変わってきます。
ニップル管の腐食が進んでいる場合は、止水栓ごと交換するのが基本です。古いニップル管を取り外す際に折れてしまうこともあるため、専門的な工具と技術が必要になります。
止水栓本体の経年劣化
止水栓本体が経年劣化により破損することで、水漏れが発生することもあります。
金属製の止水栓も、長年の使用により材質が劣化し、亀裂が入ったり、腐食が進んだりすることがあります。特に30年以上経過した止水栓では、本体の劣化による水漏れリスクが高まります。
本体の劣化による水漏れは、複数箇所から同時に水が染み出すことが多く、部分的な修理では対応できません。また、無理に操作すると破損が拡大する恐れもあります。
このような場合は、止水栓全体の交換が必要です。交換作業は配管工事を伴うため、必ず専門業者に依頼してください。
定期的な点検により、早期に劣化の兆候を発見することで、突然の水漏れトラブルを防げます。止水栓の表面に錆や変色が見られる場合は、早めの交換を検討しましょう。
今すぐできる!止水栓水漏れの応急処置と修理方法

止水栓からの水漏れを発見したら、被害を最小限に抑えるため迅速な対応が必要です。
まずは元栓を閉めて被害を最小限に
水漏れを発見したら、まず落ち着いて元栓を閉めることが最優先です。
元栓は、一戸建ての場合は敷地内の地面にあるメーターボックス内、マンションの場合は玄関脇のパイプスペース内に設置されており、sハンドルを時計回りに回すと水が止まります。
元栓を閉めたら、漏れた水をすぐに拭き取りましょう。床や壁が濡れたままだと、カビの発生や木材の腐食につながるため、乾いた布でしっかりと水分を取り除いてください。
可能であれば、扇風機やドライヤーを使って乾燥させると効果的です。特に収納スペース内での水漏れは、収納物も確認し、濡れているものは取り出して乾かします。
応急処置として、止水栓周りにタオルを巻いて漏水を吸収させる方法もあります。ただし、これはあくまで一時的な対策であり、根本的な解決にはなりません。
水漏れの状況を写真に撮っておくと、後で業者に説明する際に役立ちます。
ナットの増し締めで解決できるケース
止水栓を確認し、接続部のナットの緩みが原因と分かった場合は、適切な工具で締め直すだけで水漏れが止まることがあります。
必要な工具はモンキーレンチやスパナです。止水栓のサイズに合った工具を使用してください。一般的な止水栓では、13mmから17mm程度のサイズが多く使われています。
作業を始める前に、必ず元栓が閉まっていることを確認してください。ナットを締める際は、少しずつ力を加えていきます。一気に強く締めると、配管や止水栓を破損させる恐れがあるため注意しましょう。
締め付けの目安は、手で回らなくなってから、工具で1/4回転程度です。締めすぎるとパッキンを傷めたり、ネジ山を潰したりする原因になります。
締め直した後は、元栓を少しずつ開けて、水漏れが止まったか確認しましょう。まだ漏れている場合は、パッキンの劣化など他の原因が考えられるため、次の対処法を検討してください。
パッキン交換の手順と注意点
パッキンの劣化が原因の場合、新しいパッキンに交換することで水漏れを解消できます。
まず、交換用のパッキンを用意します。止水栓用の三角パッキン(コマパッキン)は、ホームセンターで購入できます。一般的なサイズは13mmですが、念のため古いパッキンを持参して同じものを購入すると確実です。
パッキン交換の手順
元栓を閉めて水を止めた状態で作業を開始します。
ハンドル式の止水栓の場合、まずハンドル上部の止めビスをプライヤーやマイナスドライバーで外し、ハンドルを取り外します。次に、モンキーレンチを使って袋ナットを反時計回りに回して外しましょう。
袋ナットを外すと、中から古いパッキンが出てきます。固着している場合は、ラジオペンチなどで慎重に取り外してください。
新しいパッキンを正しい向きで取り付けます。パッキンには表裏があるため、取り外した時と同じ向きで設置することが重要です。
最後に、袋ナットとハンドルを元通りに取り付けます。締め付けは適度に行い、きつく締めすぎないよう注意してください。
作業が完了したら、元栓を開けて水漏れが止まったか確認しましょう。交換後も水漏れが続く場合は、他の部品の劣化が考えられるため、専門業者への相談をおすすめします。
愛知県で止水栓の部品が買えるホームセンター
止水栓の修理に必要な部品や工具は、ホームセンターで購入できます。
カインズ名古屋堀田店
住所:愛知県名古屋市瑞穂区新開町24番55号
営業時間:資材館 8:30〜20:00
名鉄堀田駅から徒歩1分の好立地にある大型店舗。DIY用品から生活用品まで幅広い品揃えが魅力です。 フードコートも充実しており、買い物の合間に休憩することもできます。
カインズ名古屋みなと店
住所:愛知県名古屋市港区一州町1-3
営業時間:資材館: 7:00〜〜20:00
圧倒的な商品数を誇る大型店舗。工具や配管部品の種類も豊富で、専門的な部品も見つかりやすいです。 隣接するベイシアやBOOKOFFと合わせて、一日中ショッピングを楽しめます。
DCM21名古屋城北店
住所:愛知県名古屋市北区浪打町1丁目51番地
営業時間:資材館 7:00〜20:00
生活館と資材館の2棟構成で、プロ向けの建築資材も充実。早朝から営業しているため、急な修理にも対応できます。 園芸コーナーも人気で、ガーデニング用品も豊富に取り揃えています。
スーパービバホーム名古屋南店
住所:愛知県名古屋市南区豊田5丁目21-1
営業時間:資材館 6:30〜21:00
早朝から夜遅くまで営業している便利な店舗。水道関連の部品コーナーが充実しており、パッキンの種類も豊富です。 店内が広く、ゆったりと買い物ができる環境が整っています。
こんな時はプロの水道業者に相談を
止水栓の水漏れは簡単な修理で解決することもありますが、状況によっては専門的な技術や工具が必要です。無理な修理は被害を拡大させる恐れがあるため、適切な判断を行いましょう。
自力修理が危険な4つのケース
止水栓の修理には、専門知識と経験が必要な場合があります。以下の4つのケースでは、自力での修理は避け、プロに任せることをおすすめします。
1. DIYの経験がほとんどない場合
工具の扱いに慣れていない方が無理に修理を行うと、かえって被害を拡大させかねません。
止水栓の修理は、狭い場所での作業が多く、適切な力加減も必要です。工具の使い方を誤ると、配管を傷つけたり、部品を破損させたりする可能性があります。
少しでも不安を感じる場合は、最初から専門業者に依頼する方が、時間も費用も節約できることが多いです。
2. 給湯器まわりの止水栓の場合
給湯器には、水道管だけでなくガス管も接続されているため、誤った作業は重大な事故につながる恐れがあります。
給湯器の止水栓は、通常の止水栓とは構造が異なり、給湯器本体の故障と連動している可能性もあるため、専門的な知識による総合的な診断が必要です。
安全性を最優先に考え、給湯器まわりのトラブルは必ず専門業者に相談してください。
3. 内部部品が破損・腐食している場合
バルブやニップル管など、パッキン以外の部品が破損している場合は、部品交換や配管工事が不可欠です。
これらの作業には、専門的な工具(逆タップなど)や技術が必要で、経験のない方には困難でしょう。また、古い部品を取り外す際に、配管内に破片が残ってしまうリスクもあります。
部品の破損が疑われる場合は、無理をせず専門業者に診断してもらいましょう。
4. 止水栓本体の故障の場合
止水栓本体が経年劣化で故障している場合、本体ごとの交換が必要になります。
この作業は、配管の切断や接続など、大掛かりな工事を伴います。また、建物の構造によっては、壁や床の一部を開口する必要があることも多いです。
専門業者なら、最適な方法で確実に交換作業を行い、今後のトラブルも防いでくれるため安心して任せられます。
愛知県全域24時間365日受付対応!止水栓のトラブルは「あいち水道職人」へ
止水栓の水漏れでお困りの際は、地元密着で信頼と実績のある「あいち水道職人」にお任せください。私たちは愛知県全域で水道トラブルに対応している水道局指定工事店として、確かな技術とサービスでお客様の安心をお届けしています。
年中無休で24時間365日受付対応しているため、年末年始やお盆期間中の急な水漏れにも迅速に対応可能です。お電話をいただければ、最短30分から1時間ほどで現地へ駆けつけ、経験豊富なスタッフが的確に診断・修理を行います。
料金面でも安心してご利用いただけるよう、作業前には必ず詳細な見積もりを提示し、お客様にご納得いただいてから作業を開始いたします。見積もりは無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。お支払い方法も現金だけでなく、クレジットカード、銀行振込、QRコード決済、コンビニ支払いなど、お客様のご都合に合わせて選択いただけます。
止水栓の水漏れは、パッキン交換などの簡単な修理から、本体交換などの大掛かりな工事まで、幅広く対応しています。止水栓の水漏れでお困りの際は、ぜひ「あいち水道職人」にお任せください。
※本記事でご紹介している方法は、一般的な対処法の例です。
作業を行う際は、ご自身の状況や設備を確認のうえ、無理のない範囲で行ってください。
記事内容を参考に作業を行った結果生じた不具合やトラブルについては、当社では責任を負いかねます。
少しでも不安がある場合や、作業に自信がない場合は、無理をせず専門業者へ相談することをおすすめします。
関連記事


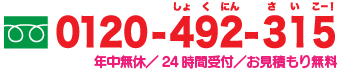

 トイレの水詰まりを解消するための方法とは
トイレの水詰まりを解消するための方法とは  トイレのオーバーフロー管が壊れたときの交...
トイレのオーバーフロー管が壊れたときの交...  「汗マネジメントの日(7月8日)」に考え...
「汗マネジメントの日(7月8日)」に考え...  水道比較サイトはこう使おう!比較ポイント...
水道比較サイトはこう使おう!比較ポイント...