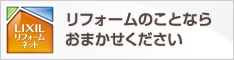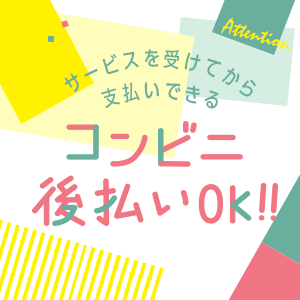水のコラム
三河湾に広がる苦潮被害|暮らしへの影響と私たちにできること【水道職人:プロ】

最近、三河湾を見ていて「海が白っぽく濁ってるな」とか、「魚が海面に浮いてる…」なんて光景を目にしたことはありませんか?
それって実は「青潮(あおしお)」と呼ばれる現象かもしれません。
「苦潮(にがしお)」という別名もあり、見た目はなんとなくきれいに見えることもあるのですが、実際は魚たちにとってとても辛い環境なんです。
愛知県の沿岸部、特に三河湾では近年この苦潮による被害がよく報告されています。
漁業への影響はもちろん、海の環境そのものが懸念されているのですが、案外この現象は私たちの日常生活とも深いつながりがあるんです。
今回は、青潮(苦潮)とは何なのか、なぜ三河湾で起きやすいのか、そして私たちにできることは何なのか、といったテーマで分かりやすくお話ししたいと思います。
目次
苦潮とは?|青潮の仕組みと特徴

「青潮(あおしお)」と聞いても、あまりピンとこない方も多いかもしれません。
青潮は、簡単に言うと海の中の酸素がとても少なくなってしまい、その結果として海水が白っぽく濁って見える現象のことです。
魚たちにとっては文字通り「息ができない」状態になってしまうため、「苦潮」という名前で呼ばれることもあります。
似たような現象として、「赤潮」は植物プランクトンが大量発生することで海が赤や茶色に染まりますが、青潮は海底で作られた硫化物などの化学物質が原因で、まるで白いモヤがかかったような独特の見た目になります。
一見すると美しく見えることもあるんですが、実際には海の中で魚たちが酸素不足で苦しんでいるサインなんです。
青潮が発生すると、海面近くに大量の魚が浮かんできたり、海岸に打ち上げられたりするほか、普段とは違う独特のにおいがすることもあります。
特に気温が高くなる夏場にこうした現象が起きやすく、なんとなく海の様子に違和感を感じたら、それは青潮のサインかもしれません。
地元の海の変化に、ぜひ一度注意を向けてみてください。
なぜ三河湾で苦潮が起こる?

実は、三河湾には青潮が起こりやすい条件がいくつも重なっているんです。
地形的な特徴や、私たちの生活から出る汚れなど、様々な要因が組み合わさることで青潮を引き起こしています。
閉鎖的な地形による影響
三河湾は伊勢湾や知多半島に囲まれた、いわば「袋のような」形をした海域です。
この地形は静かで穏やかな海を作り出し、養殖業や漁業にはとても適しているのですが、一方で海水の入れ替わりが起こりづらいという問題もあります。
外海から新鮮な海水が入ってきにくく、汚れた水や酸素の少ない水がそのまま湾内に留まってしまいがちなんですね。
特に夏になると水温がどんどん上がり、海底の酸素がどんどん消費されてしまいます。
そうして酸素不足になった水が海面に上がってくると、青潮が発生してしまうというわけです。
私たちの生活排水も原因の一つ
もう一つの大きな原因が「富栄養化」という現象。
これは、海に栄養分がたくさん流れ込むことで起こります。
「栄養があるなら良いことでは?」なんて思うかもしれませんが、実はそうではありません。
栄養が多すぎる海では、植物プランクトンなどの微生物が異常に増殖します。
そして、大量に増えた微生物が死んで海底に沈むと、それを分解するために大量の酸素が使われてしまいます。
その結果、海底が酸素不足になり、やがて青潮の原因となってしまうわけです。
この「栄養分」の多くは、実は私たちの家庭から出る生活排水や、農業で使われる肥料などに含まれています。
さらに最近では、地球温暖化の影響で海水温が上昇し、酸素不足がより深刻になっているとも言われているため、何らかの対策が必要とされています。
家庭でできる水環境の守り方

苦潮は海の問題のように見えますが、実は私たちの生活ともつながっています。
私たちの日常生活の中にも、海の環境を守るためにできることがたくさんあるんです。
小さな工夫の積み重ねが、やがて大きな変化につながるということを、ぜひ意識してみてください。
キッチンでできる簡単な工夫
青潮を防ぐためには、まず海に流れ込む汚れを減らすことから始めましょう。
例えば、お皿についた食べ残しや油汚れは、水で流す前にキッチンペーパーや古い布でしっかりと拭き取る習慣をつけてみてください。
牛乳やジュースなどの飲み残しをそのまま流すのもNG。
実は、こうした飲み残しも水質に影響を与えています。
また、料理で使った油は絶対に排水口に流さず、新聞紙などに吸わせてから燃えるゴミとして出しましょう。
「ちょっとくらいなら大丈夫」という気持ちが積み重なることで、海の環境に大きな負担をかけてしまいます。
お風呂でも環境に優しい選択を
お風呂の残り湯を洗濯に使ったり、お庭の水やりに再利用したりするのも、水の節約になって環境に優しい取り組みの一環です。
(ただし場合によっては皮脂や雑菌などによる影響もあるため残り湯の水質には注意)
また、シャンプーや石鹸を選ぶときも、できるだけ環境に配慮した製品を選んでみてはいかがでしょうか。
地域の海を守るために、今できること

青潮(苦潮)は確かに自然現象の一つですが、その背景には私たち人間の生活が大きく関わっています。
普段何気なく使っている洗剤、料理で出る油汚れ、生活排水の処理方法など、日常生活のちょっとした心がけが、実は海の環境を左右しています。
三河湾のような閉鎖的な海域では特に、私たちの生活が海の環境に与える影響は大きくなります。
だからこそ、一人ひとりの小さな意識の変化が、長期的には大きな改善につながる可能性があるんです。
「きれいな海を子どもたちに残してあげたい」「地元の漁師さんが仕事できる環境を守りたい」
そんな思いがあるなら、まずは今日からできる小さなことから始めてみませんか?
食器の汚れを拭き取ってから洗う、油を流さない、環境に優しい洗剤を選ぶ。
こうした日常の工夫が、やがて海の環境改善につながっていくはずです。
※本記事でご紹介している方法は、一般的な対処法の例です。
作業を行う際は、ご自身の状況や設備を確認のうえ、無理のない範囲で行ってください。
記事内容を参考に作業を行った結果生じた不具合やトラブルについては、当社では責任を負いかねます。
少しでも不安がある場合や、作業に自信がない場合は、無理をせず専門業者へ相談することをおすすめします。
関連記事


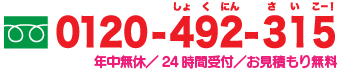

 集合住宅ならではのトイレ詰まりの注意点
集合住宅ならではのトイレ詰まりの注意点  キッチンの水漏れトラブル!早めの対処で被...
キッチンの水漏れトラブル!早めの対処で被...  蛇口から水漏れするときのチェックポイント
蛇口から水漏れするときのチェックポイント  エアコンからの水漏れは事故につながること...
エアコンからの水漏れは事故につながること...